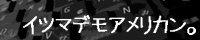感謝★(1/8)
広い石畳の向こうには、日本海。
珍しく穏やかな姿を見せている海は、何処までも青い。
真夏とは思えない涼やかな潮風が全身を包む。
「恭一、そろそろ電車、出るってよ」
背後から聞こえる声。
「おう、すぐ行く」
振り向いた先に立つ男の顔が、夏の日差しに照らされている。
その晴れやかな表情と、故郷の空気が、改めて自分の気持ちを思い知らせてくれた。
俺は、この笑顔の為に、帰って来ていると。
***********************************
『西船橋駅南口 2230 080-・・・』
夜10時過ぎ。
仕事用の携帯にメールが届く。
メッセージを認め、ポケットに携帯を突っ込んで、家を出る。
アパートの近くの青空駐車場には、俺の唯一の財産であるハイブリッドカー。
ローンは、もうじき完済。
それまでの我慢だ、そう思いながら、缶コーヒー片手に車に乗り込んだ。
国道14号線を走ること20分。
駅の出口から続く階段の脇に、それらしき女の子が立っていた。
指定された携帯番号に、車種とナンバーを記したショートメッセージを送る。
携帯を覗き込んだ彼女は、こちらに視線を送った後、目的地を記したメールを返信してきた。
「おはよーございまーす」
気だるそうに言葉を発した彼女は、後ろの座席に乗り込んだ。
「おはよ」
ナビに目的地を入力しながら、短く挨拶を返し、車を発進させる。
行き先は幕張のホテル。
ここからなら、30分もかからず着くはずだ。
湾岸道路を東に向かう。
行き交う車も、そう多くない。
ぼんやりと車窓を眺めていた後ろの彼女が、ふと口を開いた。
「あたしねぇ、お金貯めたら、田舎帰るんだ」
「へぇ・・・田舎は、何処なの?」
「青森、五所川原ってとこ」
久しぶりに聞く、平板なイントネーション。
つい、懐かしさが込み上げた。
「そう・・・でも、こっちの方が、良いんじゃない?帰ったって、何も、無いじゃん」
「そーだけどさ。でも、やっぱ、帰りたくなっちゃった。疲れるんだもん、都会は」
助手席のヘッドレストを抱えるように身を乗り出した彼女は、俺の顔を眺め、言う。
「おにーさんも、東北の人だよねぇ?」
「え、何で?」
「何か、喋り方で分かるんだよね。そーだな・・・秋田とか、その辺でしょ?」
人差し指の爪に付けられた幾つもの飾りが、対向車のヘッドライトを受けてキラキラと光る。
あどけなさが残る得意顔に一瞬視線を向けて、答えた。
「そ、白神の方」
「超近いじゃん。五能線とか、乗ったりする?」
秋田から青森にかけて、日本海沿いを走る路線。
実家のすぐ近くに駅があり、小さい頃はよく乗っていたけれど
もう長い間帰省してない事もあり、おぼろげな面影しか浮かんで来ない。
「最近、乗ってないな。随分帰ってないし」
「あたしも帰省の時くらいしか乗んないけど、すげー立派な電車とか走ってるよ、今」
「そうなんだ」
あまり思い出したくない、日本海の風景が頭を巡る。
それに被さるよう、視界の中に目的地のホテルが見えてきた。
ホテルの手前の車道脇に車を停める。
小さな鏡で丹念に自分の顔をチェックした彼女は、一つ息を吐いて、車を降りた。
「ありがと。へばねっ」
笑ってそう言いながら、勢い良くドアを閉め、歩道を歩いていく。
見も知らない男とセックスをして、金を貰う。
決して褒められた行為じゃない。
それでも、何かの目標を持っているだけ、彼女の方が立派に見えてくる。
俺は、何だ。
田舎から逃げてきて、日銭を稼ぐ為だけに、非合法な行為に加担している。
帰ろうか。
でも、帰れない。
迷いを振り切るよう、目の前に聳える高層ホテルを眺める。
ここで夜を楽しむ人間と、俺は、何が違うんだろう。
不意に起こった携帯の振動が、そんな不毛な思考を遮った。
『新浦安駅北側 2315 090-・・・』
携帯をダッシュボードに放り投げ、エンジンをかける。
溜め息を引き摺りながら、次の目的地へ向かった。
午前4時過ぎの渋谷。
意識を失いかけた若者たちが、我が物顔で道路を闊歩している。
それを横目に、うらびれたマンションの一室に向かう。
「今日は・・・12人?多いねぇ」
「給料日後の週末、だからですかね」
「他に金の使い道、無いのかってな」
俺の前に座る男は、卑しい笑みを浮かべながら、万札を数える。
「じゃ、これ、今日の分」
無造作に渡されたのは、7枚の一万円札。
「ガス代は、そっから出して」
「分かりました。ありがとうございます」
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
珍しく穏やかな姿を見せている海は、何処までも青い。
真夏とは思えない涼やかな潮風が全身を包む。
「恭一、そろそろ電車、出るってよ」
背後から聞こえる声。
「おう、すぐ行く」
振り向いた先に立つ男の顔が、夏の日差しに照らされている。
その晴れやかな表情と、故郷の空気が、改めて自分の気持ちを思い知らせてくれた。
俺は、この笑顔の為に、帰って来ていると。
***********************************
『西船橋駅南口 2230 080-・・・』
夜10時過ぎ。
仕事用の携帯にメールが届く。
メッセージを認め、ポケットに携帯を突っ込んで、家を出る。
アパートの近くの青空駐車場には、俺の唯一の財産であるハイブリッドカー。
ローンは、もうじき完済。
それまでの我慢だ、そう思いながら、缶コーヒー片手に車に乗り込んだ。
国道14号線を走ること20分。
駅の出口から続く階段の脇に、それらしき女の子が立っていた。
指定された携帯番号に、車種とナンバーを記したショートメッセージを送る。
携帯を覗き込んだ彼女は、こちらに視線を送った後、目的地を記したメールを返信してきた。
「おはよーございまーす」
気だるそうに言葉を発した彼女は、後ろの座席に乗り込んだ。
「おはよ」
ナビに目的地を入力しながら、短く挨拶を返し、車を発進させる。
行き先は幕張のホテル。
ここからなら、30分もかからず着くはずだ。
湾岸道路を東に向かう。
行き交う車も、そう多くない。
ぼんやりと車窓を眺めていた後ろの彼女が、ふと口を開いた。
「あたしねぇ、お金貯めたら、田舎帰るんだ」
「へぇ・・・田舎は、何処なの?」
「青森、五所川原ってとこ」
久しぶりに聞く、平板なイントネーション。
つい、懐かしさが込み上げた。
「そう・・・でも、こっちの方が、良いんじゃない?帰ったって、何も、無いじゃん」
「そーだけどさ。でも、やっぱ、帰りたくなっちゃった。疲れるんだもん、都会は」
助手席のヘッドレストを抱えるように身を乗り出した彼女は、俺の顔を眺め、言う。
「おにーさんも、東北の人だよねぇ?」
「え、何で?」
「何か、喋り方で分かるんだよね。そーだな・・・秋田とか、その辺でしょ?」
人差し指の爪に付けられた幾つもの飾りが、対向車のヘッドライトを受けてキラキラと光る。
あどけなさが残る得意顔に一瞬視線を向けて、答えた。
「そ、白神の方」
「超近いじゃん。五能線とか、乗ったりする?」
秋田から青森にかけて、日本海沿いを走る路線。
実家のすぐ近くに駅があり、小さい頃はよく乗っていたけれど
もう長い間帰省してない事もあり、おぼろげな面影しか浮かんで来ない。
「最近、乗ってないな。随分帰ってないし」
「あたしも帰省の時くらいしか乗んないけど、すげー立派な電車とか走ってるよ、今」
「そうなんだ」
あまり思い出したくない、日本海の風景が頭を巡る。
それに被さるよう、視界の中に目的地のホテルが見えてきた。
ホテルの手前の車道脇に車を停める。
小さな鏡で丹念に自分の顔をチェックした彼女は、一つ息を吐いて、車を降りた。
「ありがと。へばねっ」
笑ってそう言いながら、勢い良くドアを閉め、歩道を歩いていく。
見も知らない男とセックスをして、金を貰う。
決して褒められた行為じゃない。
それでも、何かの目標を持っているだけ、彼女の方が立派に見えてくる。
俺は、何だ。
田舎から逃げてきて、日銭を稼ぐ為だけに、非合法な行為に加担している。
帰ろうか。
でも、帰れない。
迷いを振り切るよう、目の前に聳える高層ホテルを眺める。
ここで夜を楽しむ人間と、俺は、何が違うんだろう。
不意に起こった携帯の振動が、そんな不毛な思考を遮った。
『新浦安駅北側 2315 090-・・・』
携帯をダッシュボードに放り投げ、エンジンをかける。
溜め息を引き摺りながら、次の目的地へ向かった。
午前4時過ぎの渋谷。
意識を失いかけた若者たちが、我が物顔で道路を闊歩している。
それを横目に、うらびれたマンションの一室に向かう。
「今日は・・・12人?多いねぇ」
「給料日後の週末、だからですかね」
「他に金の使い道、無いのかってな」
俺の前に座る男は、卑しい笑みを浮かべながら、万札を数える。
「じゃ、これ、今日の分」
無造作に渡されたのは、7枚の一万円札。
「ガス代は、そっから出して」
「分かりました。ありがとうございます」
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(2/8)
大きめの窓の向こうに、爽やかな山の風景が流れていく。
もう見飽きたものだと思っていたのに、やけに目新しく感じるのは何故だろう。
「仕事は、もう慣れたのか?」
隣に座る加賀谷は、車内で買ったリンゴジュースを飲みながら訊ねてくる。
「ああ、まぁ・・・生活のサイクルに、やっと身体がついて来たって感じかな」
「いろんな客がいるんだろ?」
「そりゃもう、話題には事欠かないな」
タクシーの運転手になってから、もうすぐ2年。
毎晩着飾って勤務先に赴くホステス、乗る度にチップと言って万札を投げて寄越すヤクザ。
去年の年末辺りは、夜間作業明けのサラリーマンに毎晩呼ばれていた。
「夜中心で走ってんの?」
「だな。競争率は高いけど、固定客も付きやすいし」
都会の夜景が目に浮かぶ。
酔っ払いに絡まれることもある、言いがかりをつけられることもある。
それでも、俺はそこで生きて行かなきゃならない。
不意に車内に差し込んでくる陽の光が、そんな嫌な現実までも和らげてくれる様だった。
***********************************
ある夜の南浦和駅。
連絡を受けたにも拘らず、それらしき女の子の姿は無かった。
予定の時刻よりも5分過ぎ、相手の携帯に連絡しようと電話を取り出した時、後部座席のドアが開く。
「すんません、ちょっと電車遅れて」
悪びれもせず乗り込んでくる、若い男。
意味が分からず混乱する俺に、彼は自分の携帯を差し出して、行き先を示す。
「この、インターんとこの、ラブホまでね」
彼らの仕事について、俺は一切のことを聞かない。
別に決められている訳ではないけれど、話しかけられない限りは口を開かないようにしている。
相手のことを酷く罵倒し続ける子もいれば、延々と泣き続ける子もいる。
そんな女にほだされて、逃避行よろしく二人で逃げたというドライバーが過去にもいたが
商品に手を出した従業員を雇い主が許すはずが無く、その末路を何度と無く聞かされてきた。
感情移入しない為の自衛手段、それが、この重苦しい沈黙の時間だ。
バックミラーに映る男の顔は、何処と無く緊張を表している。
こうやって同性を送り届けるのは初めてで、それだけに、自分の身に置き換えて考えるのは容易い。
相手の女は、どんな人間なのだろう。
性欲を満たす為だけに、男を買う。
男だって同じことをしている、そう思っても、素直に受け取れない。
ボリュームを絞ったラジオが流れる中、目的のホテルのネオンがフロントガラスにちらつき始める。
「迎えに来てくれんのも、お兄さん?」
停車した車の中で、彼はそう聞いて来た。
「今日はこの辺回るから、多分、そうかな」
「そ、分かった。じゃ、また後で」
小さく溜め息をつき、男は車を降りる。
建物に向かって歩く途中、彼は不意に振り向き、俺に視線を投げた。
もしかしたら、彼は、初めてなのかも知れない。
若い彼がこんなことをしているのは、どうしてなんだろう。
意味の無いことを考えている内に、男の姿はホテルの中へ消えていった。
今日は皆、財布の紐が固いみたいだ。
コンビニの駐車場で時間を潰しながら、煙草に火を点ける。
ポツリポツリと雨が降って来て、少し肌寒い。
眠気を飛ばすように背伸びをしたところで、待っていた連絡が入る。
時間は既に朝4時過ぎ。
彼を拾って、送り届けたら、今日の仕事は終わり。
そう思うと、不思議と睡魔も飛んでいく。
コンビニからホテルまでは10分程度だった。
その間、彼は外で待っていたのだろうか。
濡れた髪と服を気にするでもなく、車に乗り、シートに身を預ける。
少しエアコンを強くして、ギアに手をかけた。
「南浦和までで良いの?」
「お兄さん、今日は、もう仕事終わり?」
俺の問に、彼は質問で返す。
「ん・・・ああ、そうだけど」
「じゃあさ、1、2時間、車でどっか回ってよ」
雨が叩きつける窓越しに外を眺めながら、彼はそう呟いた。
「そしたら、電車で帰るから」
近くのインターから外環道に入った。
微睡む街を反時計回りに南下しながら、雨も上がり、明けて行く空に向かって走る。
「海の方、行ってみる?」
当て所の無いドライブ。
適当な俺の提案に、彼は頷いて、一言漏らす。
「そのまま、どっか遠くに、行ければなぁ」
有明で高速を降り、埠頭の突端でぼんやり早朝の海を眺める。
会話は無い。
ミラーに映る彼は、座席に足を乗せ、立てた膝に肘をついて外を見ていた。
窓を開けて、煙草に火を点ける。
流れていく煙が、白む空と同化して、すぐに行方が分からなくなった。
不意にヘッドレストに手がかかり、彼の身体が前の座席に乗り出してくる。
「オレにも、吸わせて」
彼の手が、煙草を持つ俺の手を掴み、自らの口元に近づける。
そのまま大きく吸い込んで、ゆっくりと煙を吹き出した。
すぐそこに迫った顔が、気分を揺らがせる。
男は俺の手を取ったまま、何も言わず、俺の頬に唇を寄せた。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
もう見飽きたものだと思っていたのに、やけに目新しく感じるのは何故だろう。
「仕事は、もう慣れたのか?」
隣に座る加賀谷は、車内で買ったリンゴジュースを飲みながら訊ねてくる。
「ああ、まぁ・・・生活のサイクルに、やっと身体がついて来たって感じかな」
「いろんな客がいるんだろ?」
「そりゃもう、話題には事欠かないな」
タクシーの運転手になってから、もうすぐ2年。
毎晩着飾って勤務先に赴くホステス、乗る度にチップと言って万札を投げて寄越すヤクザ。
去年の年末辺りは、夜間作業明けのサラリーマンに毎晩呼ばれていた。
「夜中心で走ってんの?」
「だな。競争率は高いけど、固定客も付きやすいし」
都会の夜景が目に浮かぶ。
酔っ払いに絡まれることもある、言いがかりをつけられることもある。
それでも、俺はそこで生きて行かなきゃならない。
不意に車内に差し込んでくる陽の光が、そんな嫌な現実までも和らげてくれる様だった。
***********************************
ある夜の南浦和駅。
連絡を受けたにも拘らず、それらしき女の子の姿は無かった。
予定の時刻よりも5分過ぎ、相手の携帯に連絡しようと電話を取り出した時、後部座席のドアが開く。
「すんません、ちょっと電車遅れて」
悪びれもせず乗り込んでくる、若い男。
意味が分からず混乱する俺に、彼は自分の携帯を差し出して、行き先を示す。
「この、インターんとこの、ラブホまでね」
彼らの仕事について、俺は一切のことを聞かない。
別に決められている訳ではないけれど、話しかけられない限りは口を開かないようにしている。
相手のことを酷く罵倒し続ける子もいれば、延々と泣き続ける子もいる。
そんな女にほだされて、逃避行よろしく二人で逃げたというドライバーが過去にもいたが
商品に手を出した従業員を雇い主が許すはずが無く、その末路を何度と無く聞かされてきた。
感情移入しない為の自衛手段、それが、この重苦しい沈黙の時間だ。
バックミラーに映る男の顔は、何処と無く緊張を表している。
こうやって同性を送り届けるのは初めてで、それだけに、自分の身に置き換えて考えるのは容易い。
相手の女は、どんな人間なのだろう。
性欲を満たす為だけに、男を買う。
男だって同じことをしている、そう思っても、素直に受け取れない。
ボリュームを絞ったラジオが流れる中、目的のホテルのネオンがフロントガラスにちらつき始める。
「迎えに来てくれんのも、お兄さん?」
停車した車の中で、彼はそう聞いて来た。
「今日はこの辺回るから、多分、そうかな」
「そ、分かった。じゃ、また後で」
小さく溜め息をつき、男は車を降りる。
建物に向かって歩く途中、彼は不意に振り向き、俺に視線を投げた。
もしかしたら、彼は、初めてなのかも知れない。
若い彼がこんなことをしているのは、どうしてなんだろう。
意味の無いことを考えている内に、男の姿はホテルの中へ消えていった。
今日は皆、財布の紐が固いみたいだ。
コンビニの駐車場で時間を潰しながら、煙草に火を点ける。
ポツリポツリと雨が降って来て、少し肌寒い。
眠気を飛ばすように背伸びをしたところで、待っていた連絡が入る。
時間は既に朝4時過ぎ。
彼を拾って、送り届けたら、今日の仕事は終わり。
そう思うと、不思議と睡魔も飛んでいく。
コンビニからホテルまでは10分程度だった。
その間、彼は外で待っていたのだろうか。
濡れた髪と服を気にするでもなく、車に乗り、シートに身を預ける。
少しエアコンを強くして、ギアに手をかけた。
「南浦和までで良いの?」
「お兄さん、今日は、もう仕事終わり?」
俺の問に、彼は質問で返す。
「ん・・・ああ、そうだけど」
「じゃあさ、1、2時間、車でどっか回ってよ」
雨が叩きつける窓越しに外を眺めながら、彼はそう呟いた。
「そしたら、電車で帰るから」
近くのインターから外環道に入った。
微睡む街を反時計回りに南下しながら、雨も上がり、明けて行く空に向かって走る。
「海の方、行ってみる?」
当て所の無いドライブ。
適当な俺の提案に、彼は頷いて、一言漏らす。
「そのまま、どっか遠くに、行ければなぁ」
有明で高速を降り、埠頭の突端でぼんやり早朝の海を眺める。
会話は無い。
ミラーに映る彼は、座席に足を乗せ、立てた膝に肘をついて外を見ていた。
窓を開けて、煙草に火を点ける。
流れていく煙が、白む空と同化して、すぐに行方が分からなくなった。
不意にヘッドレストに手がかかり、彼の身体が前の座席に乗り出してくる。
「オレにも、吸わせて」
彼の手が、煙草を持つ俺の手を掴み、自らの口元に近づける。
そのまま大きく吸い込んで、ゆっくりと煙を吹き出した。
すぐそこに迫った顔が、気分を揺らがせる。
男は俺の手を取ったまま、何も言わず、俺の頬に唇を寄せた。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(3/8)
本来降りるべき駅に近づいてくる。
「本当に、良いのか?」
「良いよ。俺が顔出したところで、誰も喜ばないから」
帰省、と言っても、実家に顔を出すことはしない。
高校卒業と共に上京し、離れた家族。
帰ったのは、母が入院した時と、妹が結婚した時だけ。
今更合わせる顔も無い、そう思うほど、足は遠のいていく一方だ。
「ここで弁当貰うんだろ?」
「ああ、そうだった」
この路線では、各駅で様々な駅弁を販売している。
それぞれに地元の食材が使われており、懐かしい味のオンパレード。
電車が止まると、隣に座る旧友が席を立つ。
「・・・ま、お前がそう言うなら、無理は言わないけど」
そう言いながら俺の肩を叩き、彼はホームへ下りていった。
家族が嫌いな訳じゃない。
ただ、母の微笑みが怖い、それだけだ。
***********************************
あれは、小学5年生の冬。
吹雪が窓を揺らす音で、なかなか寝付けなかった夜だった。
母を真ん中に、俺と妹がその両隣に横になる。
父が出張で家を空ける時は、決まってそんな風に布団を敷いていた。
母に背を向けるよう寝返りを打ったタイミングで、布団の中に何かが入ってくる気配を感じた。
その手が、後ろから抱き付くように伸びてくる。
「おかあ、さん・・・?」
「眠れないの?恭一」
パジャマの上から身体を優しく撫でながら、彼女はその顔を俺の頭に擦り付ける。
「な、に?」
言い知れない雰囲気が、恐怖を生んだ。
あんなに聞き慣れた声が、いつもと違って聞こえる。
背中に纏わりつく、温かく、柔らかな感触。
大好きだけれど、でも、恥ずかしさをもたらして来る心地良さ。
腹を撫でていた手が、下半身へ下りていく。
何処に向かっているのか気がついた頭が、身体よりも早く口を反応させる。
「やめてよっ」
「あんまり大きな声出しちゃ、ダメ。麻衣が起きるでしょ」
落ち着いた口調で言う母の腕が、俺の身体を押さえつける。
「そんなとこ・・・やだ」
「大丈夫よ。この間、ちゃんと、大人になったじゃない」
1ヶ月くらい前。
朝起きると、下着が濡れ、見たことも無い白い液体が付いていた。
恥ずかしくて何も言えなかった俺を、母は優しい眼差しで風呂へ連れて行く。
下着を脱がされ、自身の身体の変化の証が、お湯で洗い流される。
「心配しなくて良いのよ。これは、恭一が大きくなった証拠なの」
柔らかく撫でられている内に、経験の無い感覚で身体が震えた。
怖くなって、母から身体を離す。
それでも彼女は、変らない視線を俺に向けたまま、何処か満足そうな表情をしていた。
片腕で強く抱き締められたまま、母の手は変化を遂げた部分を弄り始める。
あの時の感覚が、心を不安で覆っていく。
首を振っても、動きは止まない。
身体を縮ませて堪えようと脚を折り曲げようとすると、脚が絡み、阻まれる。
腰の周りが緊張で動かなくなる頃、母の声が耳元で響いた。
「気持ち良い?」
分からなかった。
こんな気分が、気持ち良い?
声も出ない中、身体を捩って質問に答える。
「その内、何回もしたくなるくらい、好きになるわよ」
手の動きが俄かに早くなる。
痛さでもない、痒さでもない、経験の無い刺激が身体を襲う。
「ん、う・・・っ」
妹を起こさないように、極力我慢した声が布団の中に篭る。
小さなモノから流れ出したものが、気持ちの悪い感触を下半身に残した。
自慰行為をするようになったのは、それからどれくらい経ってからだろう。
正体不明の刺激を、快感として受け止められるようになるまで、時間はかからなかった。
その度、母から受けた行為を思い出す。
この快楽の蓋を開けたのは、自分の肉親。
例えようの無い恥ずかしさと、誰にも言えない秘密を抱えてしまった恐ろしさ。
けれど、彼女の残酷な仕打ちは、それだけでは終わらなかった。
それは、俺と、彼女の人生を大きく狂わせたのだろうと、思う。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
「本当に、良いのか?」
「良いよ。俺が顔出したところで、誰も喜ばないから」
帰省、と言っても、実家に顔を出すことはしない。
高校卒業と共に上京し、離れた家族。
帰ったのは、母が入院した時と、妹が結婚した時だけ。
今更合わせる顔も無い、そう思うほど、足は遠のいていく一方だ。
「ここで弁当貰うんだろ?」
「ああ、そうだった」
この路線では、各駅で様々な駅弁を販売している。
それぞれに地元の食材が使われており、懐かしい味のオンパレード。
電車が止まると、隣に座る旧友が席を立つ。
「・・・ま、お前がそう言うなら、無理は言わないけど」
そう言いながら俺の肩を叩き、彼はホームへ下りていった。
家族が嫌いな訳じゃない。
ただ、母の微笑みが怖い、それだけだ。
***********************************
あれは、小学5年生の冬。
吹雪が窓を揺らす音で、なかなか寝付けなかった夜だった。
母を真ん中に、俺と妹がその両隣に横になる。
父が出張で家を空ける時は、決まってそんな風に布団を敷いていた。
母に背を向けるよう寝返りを打ったタイミングで、布団の中に何かが入ってくる気配を感じた。
その手が、後ろから抱き付くように伸びてくる。
「おかあ、さん・・・?」
「眠れないの?恭一」
パジャマの上から身体を優しく撫でながら、彼女はその顔を俺の頭に擦り付ける。
「な、に?」
言い知れない雰囲気が、恐怖を生んだ。
あんなに聞き慣れた声が、いつもと違って聞こえる。
背中に纏わりつく、温かく、柔らかな感触。
大好きだけれど、でも、恥ずかしさをもたらして来る心地良さ。
腹を撫でていた手が、下半身へ下りていく。
何処に向かっているのか気がついた頭が、身体よりも早く口を反応させる。
「やめてよっ」
「あんまり大きな声出しちゃ、ダメ。麻衣が起きるでしょ」
落ち着いた口調で言う母の腕が、俺の身体を押さえつける。
「そんなとこ・・・やだ」
「大丈夫よ。この間、ちゃんと、大人になったじゃない」
1ヶ月くらい前。
朝起きると、下着が濡れ、見たことも無い白い液体が付いていた。
恥ずかしくて何も言えなかった俺を、母は優しい眼差しで風呂へ連れて行く。
下着を脱がされ、自身の身体の変化の証が、お湯で洗い流される。
「心配しなくて良いのよ。これは、恭一が大きくなった証拠なの」
柔らかく撫でられている内に、経験の無い感覚で身体が震えた。
怖くなって、母から身体を離す。
それでも彼女は、変らない視線を俺に向けたまま、何処か満足そうな表情をしていた。
片腕で強く抱き締められたまま、母の手は変化を遂げた部分を弄り始める。
あの時の感覚が、心を不安で覆っていく。
首を振っても、動きは止まない。
身体を縮ませて堪えようと脚を折り曲げようとすると、脚が絡み、阻まれる。
腰の周りが緊張で動かなくなる頃、母の声が耳元で響いた。
「気持ち良い?」
分からなかった。
こんな気分が、気持ち良い?
声も出ない中、身体を捩って質問に答える。
「その内、何回もしたくなるくらい、好きになるわよ」
手の動きが俄かに早くなる。
痛さでもない、痒さでもない、経験の無い刺激が身体を襲う。
「ん、う・・・っ」
妹を起こさないように、極力我慢した声が布団の中に篭る。
小さなモノから流れ出したものが、気持ちの悪い感触を下半身に残した。
自慰行為をするようになったのは、それからどれくらい経ってからだろう。
正体不明の刺激を、快感として受け止められるようになるまで、時間はかからなかった。
その度、母から受けた行為を思い出す。
この快楽の蓋を開けたのは、自分の肉親。
例えようの無い恥ずかしさと、誰にも言えない秘密を抱えてしまった恐ろしさ。
けれど、彼女の残酷な仕打ちは、それだけでは終わらなかった。
それは、俺と、彼女の人生を大きく狂わせたのだろうと、思う。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(4/8)
ダシが染みたご飯の上に乗る大量のアワビ。
駅弁なんてそれほど興味は無かったけれど、これはなかなかいける。
「うん、美味い」
「地元のくせに、食ったこと無いの?」
「この電車に乗るのも、初めてだからな」
俺の言葉に苦笑する旧友は、僅かに陽が傾きかけた広い車窓に目を移す。
「別に、無理して帰って来なくて、良いんだぞ?」
加賀谷は、高校以来付き合いのある友達だ。
上京してからしばらくは連絡も取っていなかったけれど
妹の結婚式で新郎の会社の先輩として列席していた偶然が、縁を呼び戻してくれた。
荒んだ生活の中で、小さなスピーカーから聞こえて来る懐かしい声。
それが、どれだけ俺を救ってくれたか、分からない。
彼は、俺を気遣って、その言葉を口にしたのだろう。
分かっていても、辛かった。
「そんなこと、言うなよ」
再び俺に顔を向けた彼の目が、少し細くなる。
「お前に会う為に、帰って来てるんだから」
***********************************
今から思えば、母は寂しかったのかも知れない。
相変わらず家を空けがちな父。
中学生になった俺と妹は、自室を持ち、あまり家族との時間を取らなくなる年頃。
家族全員が揃って食事をすることも、滅多に無くなっていった。
高校受験を控えた俺は、夜中まで勉強をする日が続いていた。
希望していた学校には、受かるか受からないかの瀬戸際。
そんな俺を気遣ってくれる母は、毎晩夜食を作っては差し入れてくれた。
あの時と同じ、雪の夜。
積もっていく程に、静けさが覆い被さってくる。
眠気を抑えつける様に音楽を聴きながら机に向かう背中に、気配を感じる。
振り向くと、戸口に母が立っていた。
「調子はどう?」
微笑む彼女は、俺の顔の綻びを合図にしたように、部屋に入って来た。
温かいお茶とおにぎりが、長い夜への気力を満たしてくれるようだった。
ベッドに座り、その様子を伺っていた母が、ふと口を開いた。
「恭一、彼女はいるの?」
「別に・・・そんなの、いないよ」
奥手、という訳では無かったと思う。
女の子に興味が無かった訳でも無い。
ただ、小さな頃の体験を未だに引き摺っていることが関係しているかどうかは、分からなかった。
その微笑みを怖いと思ったのは、初めてだった。
不意に立ち上がった母は、椅子に座った俺の手を取る。
「どうしたの?」
「じゃあ、まだセックスもしたこと無いのね」
親から発せられる、あまりに直接的な言葉。
自分でも口にすることの無いその一言に、動揺で声が出なかった。
女の身体を、淫らな行為を想像することは、男の本能。
それでも、近づいてくるその身体に欲情することが、どんなに忌まわしいことなのか。
「何・・・やめろって」
振り払う手が震えた。
初めての曖昧な快楽の味が、拒絶を阻む。
親子なのに。
混乱する頭は、背徳感すら奪い去る。
「かあ、さん・・・こんな」
「大丈夫、怖くないわ。恭一」
母の胸に抱えられた顔に、その感触が絡みつく。
記憶は断片的だ。
奥底に刻み付けられているのだろうが、きっと、全てを思い出したら、俺は狂う。
ただ、射精した時の絶望感だけは、はっきりと覚えていて
それ以来、俺は女の身体に欲情できなくなった。
未だに、母以外の女とセックスをしたことは、無い。
結局、俺は希望していた高校には進まず、青森にある全寮制の高校へ入った。
母と同じ屋根の下にいることが、耐えられなかった。
年末に帰省しても、日帰りで寮へ戻る。
上京してからは、地元を思い出すことすらしなかった。
忘れたい過去。
忘れられない、悪夢。
逃げる以外に道は無かった。
母が入院したと連絡を受けたのは、俺が成人するかしないか、そのくらいだったと思う。
精神を病んでしまった彼女は、記憶の中にある姿とは別人だった。
何が原因なのか分からない、父はそう言っていたが、母の虚ろな目は、明らかにそれを物語っていた。
全ての原因は、俺にある、と。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
駅弁なんてそれほど興味は無かったけれど、これはなかなかいける。
「うん、美味い」
「地元のくせに、食ったこと無いの?」
「この電車に乗るのも、初めてだからな」
俺の言葉に苦笑する旧友は、僅かに陽が傾きかけた広い車窓に目を移す。
「別に、無理して帰って来なくて、良いんだぞ?」
加賀谷は、高校以来付き合いのある友達だ。
上京してからしばらくは連絡も取っていなかったけれど
妹の結婚式で新郎の会社の先輩として列席していた偶然が、縁を呼び戻してくれた。
荒んだ生活の中で、小さなスピーカーから聞こえて来る懐かしい声。
それが、どれだけ俺を救ってくれたか、分からない。
彼は、俺を気遣って、その言葉を口にしたのだろう。
分かっていても、辛かった。
「そんなこと、言うなよ」
再び俺に顔を向けた彼の目が、少し細くなる。
「お前に会う為に、帰って来てるんだから」
***********************************
今から思えば、母は寂しかったのかも知れない。
相変わらず家を空けがちな父。
中学生になった俺と妹は、自室を持ち、あまり家族との時間を取らなくなる年頃。
家族全員が揃って食事をすることも、滅多に無くなっていった。
高校受験を控えた俺は、夜中まで勉強をする日が続いていた。
希望していた学校には、受かるか受からないかの瀬戸際。
そんな俺を気遣ってくれる母は、毎晩夜食を作っては差し入れてくれた。
あの時と同じ、雪の夜。
積もっていく程に、静けさが覆い被さってくる。
眠気を抑えつける様に音楽を聴きながら机に向かう背中に、気配を感じる。
振り向くと、戸口に母が立っていた。
「調子はどう?」
微笑む彼女は、俺の顔の綻びを合図にしたように、部屋に入って来た。
温かいお茶とおにぎりが、長い夜への気力を満たしてくれるようだった。
ベッドに座り、その様子を伺っていた母が、ふと口を開いた。
「恭一、彼女はいるの?」
「別に・・・そんなの、いないよ」
奥手、という訳では無かったと思う。
女の子に興味が無かった訳でも無い。
ただ、小さな頃の体験を未だに引き摺っていることが関係しているかどうかは、分からなかった。
その微笑みを怖いと思ったのは、初めてだった。
不意に立ち上がった母は、椅子に座った俺の手を取る。
「どうしたの?」
「じゃあ、まだセックスもしたこと無いのね」
親から発せられる、あまりに直接的な言葉。
自分でも口にすることの無いその一言に、動揺で声が出なかった。
女の身体を、淫らな行為を想像することは、男の本能。
それでも、近づいてくるその身体に欲情することが、どんなに忌まわしいことなのか。
「何・・・やめろって」
振り払う手が震えた。
初めての曖昧な快楽の味が、拒絶を阻む。
親子なのに。
混乱する頭は、背徳感すら奪い去る。
「かあ、さん・・・こんな」
「大丈夫、怖くないわ。恭一」
母の胸に抱えられた顔に、その感触が絡みつく。
記憶は断片的だ。
奥底に刻み付けられているのだろうが、きっと、全てを思い出したら、俺は狂う。
ただ、射精した時の絶望感だけは、はっきりと覚えていて
それ以来、俺は女の身体に欲情できなくなった。
未だに、母以外の女とセックスをしたことは、無い。
結局、俺は希望していた高校には進まず、青森にある全寮制の高校へ入った。
母と同じ屋根の下にいることが、耐えられなかった。
年末に帰省しても、日帰りで寮へ戻る。
上京してからは、地元を思い出すことすらしなかった。
忘れたい過去。
忘れられない、悪夢。
逃げる以外に道は無かった。
母が入院したと連絡を受けたのは、俺が成人するかしないか、そのくらいだったと思う。
精神を病んでしまった彼女は、記憶の中にある姿とは別人だった。
何が原因なのか分からない、父はそう言っていたが、母の虚ろな目は、明らかにそれを物語っていた。
全ての原因は、俺にある、と。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(5/8)
窓の外を流れるのは、リンゴの木。
青い実をたわわにつけた背の低い林が、一面広がっている。
「そう言えば、リンゴ」
「ん?今年も行くぞ?」
「そうじゃなくて。食いきれねぇって、あんな量」
お歳暮代わりだと言って、年末に加賀谷が送ってくる大量のリンゴ。
一人暮らしの俺に、到底食べ切れる量では無かった。
毎年同じことを言っているような気がするのに、やっぱり毎年送られてくる。
「しょうがねぇよ。オレんとこには、3箱来るんだぞ?」
彼の祖父は、津軽でリンゴ農家をやっている。
そこで出荷できないハネ物が孫の所に送られてくるということも、毎度聞く話だ。
「客に配ったりしたらどうだ?」
「もう、やってる」
「・・・断ったりしたら、爺様に悪いだろ」
小さな頃から親しんできたであろう光景に、愛おしげに視線を流す旧友。
「あの人が、オレの唯一の、味方なんだよ」
***********************************
彼の唇は、震えていた。
突然のことに声も出ない俺に、男は耳元で囁く。
「こっち、向いてよ」
振り向けば、何をされるかという想像をするのは簡単だった。
掴まれたままの手にある煙草から、細い煙が立ち上る。
「・・・灰、落ちる、から」
誤魔化す様にそう言いながら、煙草を灰皿に入れる。
何かを諦めるような表情をした彼は、後部座席のシートに身を任せた。
「良いよな。あんたにとっちゃ、他人事だもんな」
そう言いながら、彼はポケットから札を取出し、助手席に放り投げる。
「オッサンとヤった金で飯食うなんて・・・最低だ」
エンジンをかけることも、新しい煙草に火を点けることもできず
薄い色が付いてきた空を泳ぐカモメを眺めていた。
「それ、持ってって良いよ。今日の、お礼」
静寂を破る呟きに、どう言葉を返していいのか分からないまま
助手席のシートの下にまで散らばった万札を、一枚一枚拾い上げ、彼に差し出した。
「金は、金だろ。これは、君のだ」
「まともな男には、分かんねぇんだろうな」
女と恋愛して、セックスして、結婚して、子供作って・・・それが彼の言うまともな男なら
俺はもう、端からまともじゃない。
向けられた手を、彼はそのまま自分の方へ引っ張る。
俺の身体は後部座席側に引き摺られるように傾き、再び、彼の顔が眼前に迫った。
「じゃあ、その金で、オレを買ってよ」
躊躇うことなく、唇が重ねられる。
懐かしい柔らかな感触が、遠い過去の背徳感を呼び起こさせた。
男に欲情したことは、一度も無い。
女に欲情した記憶は、一人の身体だけ。
それなのに、抗う気持ちは、自分でも驚くほど僅かだった。
歪んだ性欲を更に歪めることで、何処かに落ち着けるのかも知れない、そう、思っていた。
助手席に場所を移した彼の手が、俺の頬を包む。
傾げた顔が近づいてきて、再び唇が触れ合った。
「男は、初めて?」
薄い視界の中に浮かぶ男に、微かな頷きで答えを返す。
「・・・そ」
少しだけ口角を上げた彼は、その唇を開き、舌で俺の唇を撫でる。
湿った感触に誘われるよう、口を開き、彼を受け入れる。
舌が触れ合う、ザラついた感覚。
口の隙間から漏れる吐息が、徐々に身体の昂りを煽っていく。
目を閉じることは出来なかった。
若い男と向き合っているという事実を認識出来ないと、不徳な記憶が顔を出す。
それが、ただひたすらに、怖かったからだ。
窓の外は、もう大分明るい。
中途半端に倒されたシートに横たわる俺の身体。
パーカーの下のTシャツの中に熱を帯びた手が入ってきて、静かに身体を弄る。
唇が首筋を這い、やがて肩口へと降りていく。
うなじを甘噛みする彼の明るい髪が視界の端にチラつく度、迷いが薄くなる。
シートに投げ出していた手を、彼の身体に添えた。
顔を上げた彼は、何となく満足そうな表情をしながら、その頭を胸元に沈み込ませる。
彼の舌に初めて気が付かされる、直接的な刺激とは違う類の快感。
唾液を纏った舌が、乳首をじっくりと愛撫する。
こんな所、感じるもんなのか。
深い呼吸が、止まらない。
指で軽く弾かれ、つい声が出る。
蠢く頭を抱えるように手を回すと、唇が突起を引っ張り上げる。
諦めていた性的な悦び。
屈折した快楽が、身体を包んでいく。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
青い実をたわわにつけた背の低い林が、一面広がっている。
「そう言えば、リンゴ」
「ん?今年も行くぞ?」
「そうじゃなくて。食いきれねぇって、あんな量」
お歳暮代わりだと言って、年末に加賀谷が送ってくる大量のリンゴ。
一人暮らしの俺に、到底食べ切れる量では無かった。
毎年同じことを言っているような気がするのに、やっぱり毎年送られてくる。
「しょうがねぇよ。オレんとこには、3箱来るんだぞ?」
彼の祖父は、津軽でリンゴ農家をやっている。
そこで出荷できないハネ物が孫の所に送られてくるということも、毎度聞く話だ。
「客に配ったりしたらどうだ?」
「もう、やってる」
「・・・断ったりしたら、爺様に悪いだろ」
小さな頃から親しんできたであろう光景に、愛おしげに視線を流す旧友。
「あの人が、オレの唯一の、味方なんだよ」
***********************************
彼の唇は、震えていた。
突然のことに声も出ない俺に、男は耳元で囁く。
「こっち、向いてよ」
振り向けば、何をされるかという想像をするのは簡単だった。
掴まれたままの手にある煙草から、細い煙が立ち上る。
「・・・灰、落ちる、から」
誤魔化す様にそう言いながら、煙草を灰皿に入れる。
何かを諦めるような表情をした彼は、後部座席のシートに身を任せた。
「良いよな。あんたにとっちゃ、他人事だもんな」
そう言いながら、彼はポケットから札を取出し、助手席に放り投げる。
「オッサンとヤった金で飯食うなんて・・・最低だ」
エンジンをかけることも、新しい煙草に火を点けることもできず
薄い色が付いてきた空を泳ぐカモメを眺めていた。
「それ、持ってって良いよ。今日の、お礼」
静寂を破る呟きに、どう言葉を返していいのか分からないまま
助手席のシートの下にまで散らばった万札を、一枚一枚拾い上げ、彼に差し出した。
「金は、金だろ。これは、君のだ」
「まともな男には、分かんねぇんだろうな」
女と恋愛して、セックスして、結婚して、子供作って・・・それが彼の言うまともな男なら
俺はもう、端からまともじゃない。
向けられた手を、彼はそのまま自分の方へ引っ張る。
俺の身体は後部座席側に引き摺られるように傾き、再び、彼の顔が眼前に迫った。
「じゃあ、その金で、オレを買ってよ」
躊躇うことなく、唇が重ねられる。
懐かしい柔らかな感触が、遠い過去の背徳感を呼び起こさせた。
男に欲情したことは、一度も無い。
女に欲情した記憶は、一人の身体だけ。
それなのに、抗う気持ちは、自分でも驚くほど僅かだった。
歪んだ性欲を更に歪めることで、何処かに落ち着けるのかも知れない、そう、思っていた。
助手席に場所を移した彼の手が、俺の頬を包む。
傾げた顔が近づいてきて、再び唇が触れ合った。
「男は、初めて?」
薄い視界の中に浮かぶ男に、微かな頷きで答えを返す。
「・・・そ」
少しだけ口角を上げた彼は、その唇を開き、舌で俺の唇を撫でる。
湿った感触に誘われるよう、口を開き、彼を受け入れる。
舌が触れ合う、ザラついた感覚。
口の隙間から漏れる吐息が、徐々に身体の昂りを煽っていく。
目を閉じることは出来なかった。
若い男と向き合っているという事実を認識出来ないと、不徳な記憶が顔を出す。
それが、ただひたすらに、怖かったからだ。
窓の外は、もう大分明るい。
中途半端に倒されたシートに横たわる俺の身体。
パーカーの下のTシャツの中に熱を帯びた手が入ってきて、静かに身体を弄る。
唇が首筋を這い、やがて肩口へと降りていく。
うなじを甘噛みする彼の明るい髪が視界の端にチラつく度、迷いが薄くなる。
シートに投げ出していた手を、彼の身体に添えた。
顔を上げた彼は、何となく満足そうな表情をしながら、その頭を胸元に沈み込ませる。
彼の舌に初めて気が付かされる、直接的な刺激とは違う類の快感。
唾液を纏った舌が、乳首をじっくりと愛撫する。
こんな所、感じるもんなのか。
深い呼吸が、止まらない。
指で軽く弾かれ、つい声が出る。
蠢く頭を抱えるように手を回すと、唇が突起を引っ張り上げる。
諦めていた性的な悦び。
屈折した快楽が、身体を包んでいく。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(6/8)
夏の夜を過ごす民宿は、海からすぐそこの場所にあった。
木造の建物は、歩く度に床板が軋む音が響くほど、年季が入っている。
「どうやって、こんなとこ見つけてくるんだ?」
「お客さんが勧めてくれたんだよ」
秋田で保険の外交員をしている加賀谷は
俺が帰省する度、客から勧められたポイントを盛り込んだ旅行日程を考えてくれる。
今日、日本海沿いを走ってきた五能線に乗ろうと提案してきたのも、彼だ。
「如何にも田舎って感じで、良いだろ?」
夕日が沈み行く海を背に、彼はそう笑う。
夕食までの短い時間、俺たちは海岸で海を眺めていた。
耳から入る波音が、水平線の向こうに連れ去ってくれるような感覚を引き起こす。
悪い気分じゃない。
少しの現実逃避くらい、許されるはずだ。
***********************************
男の手が、ベルトにかかる。
次に来るであろう行為を想像して、思わず息を飲んだ。
自分のモノが、彼の手に包まれる。
ゆっくりと上下する手の動きに、鼓動は引っ張られるように早くなっていく。
彷徨う視界の中に彼の顔が入って来た。
「キス、して」
半開きの唇が能動的な行為を誘う。
顎を突き出すように、彼の唇に自分の唇を重ねた。
より一層の快楽を求め、互いの舌を絡ませ合う。
卑猥な水音と、喉の奥から漏れる呻き声と、荒い息遣い。
商売道具でもある車の中には、非現実的な音が充満していた。
徐々に動きが激しくなる彼の頭を見下ろす。
耳につけたピアスが朝日を反射して、点滅を繰り返している。
見上げる視線を受け止める度に、誤った快感に囚われていくようだった。
絶頂が近づくと、つい首を振ってしまう。
昔からの癖だ。
達することで、あの時の絶望感を思い出してしまうからだろうか。
その仕草を、彼は違うように受け留めたらしい。
動きを止め、尋ねる。
「まだ・・・?」
「いや、もう・・・たの、む」
もどかしさで、声が震えた。
「そのまま出して、良いから」
そう言った彼は、先端にそっとキスをして、再びモノを口に含む。
すぐにやってきた快楽の終点が、頭の中を白くさせた。
通勤客でごった返す南浦和駅に彼を送り届けて、自宅へ戻る途中。
不意に笑いが込み上げてきた。
俺の欲求を満たしたのは、母の身体と、若い男の口。
それでも、心は空虚なまま。
満たしてくれる存在は、見当たらない。
異常すぎる。
自虐的な思考が突き抜けて、笑いが止まらない。
何なんだ、これ。
俺は、一生、このままか。
それから、あの若い男に会うことは無かった。
たまたまなのか、足を洗ったのか、何処か遠くへ行ったのか。
「何で、オレ、こんな風になったんだろう」
寂しげに前を見る助手席の男の顔が浮かぶ。
「男しか、好きになれないなんて」
俺からすれば、彼はまだ、まともだ。
例え同性でも、誰かを好きになることが出来る。
冬の初めの、ある朝。
仕事終わりに向かった渋谷のマンションは、もぬけの殻だった。
「ガサが入るかも知れない」
元締めの男がそう話していたのは、2、3日前だった気がする。
実際に摘発されたのか、その前にトンズラをかましたのか、俺が知る術はない。
「タダ働きかよ」
独り言が、虚しく空き部屋に響く。
手元に残る、仕事用の携帯電話。
中には、数多くの番号が登録されている。
コンクリート剥き出しの柱に打ち付けると、あっけ無い程簡単に、携帯は折れた。
突然食い扶持を失っても、気分は何処となく落ち着いていた。
これからどうするかと言う不安と、やっとこの仕事から解放されたという喜びが、平衡したのかも知れない。
幸い、車のローンの支払いは終わったばかり。
偶然目にした自動車学校の看板を見上げながら、自分の行く末を、探した。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
木造の建物は、歩く度に床板が軋む音が響くほど、年季が入っている。
「どうやって、こんなとこ見つけてくるんだ?」
「お客さんが勧めてくれたんだよ」
秋田で保険の外交員をしている加賀谷は
俺が帰省する度、客から勧められたポイントを盛り込んだ旅行日程を考えてくれる。
今日、日本海沿いを走ってきた五能線に乗ろうと提案してきたのも、彼だ。
「如何にも田舎って感じで、良いだろ?」
夕日が沈み行く海を背に、彼はそう笑う。
夕食までの短い時間、俺たちは海岸で海を眺めていた。
耳から入る波音が、水平線の向こうに連れ去ってくれるような感覚を引き起こす。
悪い気分じゃない。
少しの現実逃避くらい、許されるはずだ。
***********************************
男の手が、ベルトにかかる。
次に来るであろう行為を想像して、思わず息を飲んだ。
自分のモノが、彼の手に包まれる。
ゆっくりと上下する手の動きに、鼓動は引っ張られるように早くなっていく。
彷徨う視界の中に彼の顔が入って来た。
「キス、して」
半開きの唇が能動的な行為を誘う。
顎を突き出すように、彼の唇に自分の唇を重ねた。
より一層の快楽を求め、互いの舌を絡ませ合う。
卑猥な水音と、喉の奥から漏れる呻き声と、荒い息遣い。
商売道具でもある車の中には、非現実的な音が充満していた。
徐々に動きが激しくなる彼の頭を見下ろす。
耳につけたピアスが朝日を反射して、点滅を繰り返している。
見上げる視線を受け止める度に、誤った快感に囚われていくようだった。
絶頂が近づくと、つい首を振ってしまう。
昔からの癖だ。
達することで、あの時の絶望感を思い出してしまうからだろうか。
その仕草を、彼は違うように受け留めたらしい。
動きを止め、尋ねる。
「まだ・・・?」
「いや、もう・・・たの、む」
もどかしさで、声が震えた。
「そのまま出して、良いから」
そう言った彼は、先端にそっとキスをして、再びモノを口に含む。
すぐにやってきた快楽の終点が、頭の中を白くさせた。
通勤客でごった返す南浦和駅に彼を送り届けて、自宅へ戻る途中。
不意に笑いが込み上げてきた。
俺の欲求を満たしたのは、母の身体と、若い男の口。
それでも、心は空虚なまま。
満たしてくれる存在は、見当たらない。
異常すぎる。
自虐的な思考が突き抜けて、笑いが止まらない。
何なんだ、これ。
俺は、一生、このままか。
それから、あの若い男に会うことは無かった。
たまたまなのか、足を洗ったのか、何処か遠くへ行ったのか。
「何で、オレ、こんな風になったんだろう」
寂しげに前を見る助手席の男の顔が浮かぶ。
「男しか、好きになれないなんて」
俺からすれば、彼はまだ、まともだ。
例え同性でも、誰かを好きになることが出来る。
冬の初めの、ある朝。
仕事終わりに向かった渋谷のマンションは、もぬけの殻だった。
「ガサが入るかも知れない」
元締めの男がそう話していたのは、2、3日前だった気がする。
実際に摘発されたのか、その前にトンズラをかましたのか、俺が知る術はない。
「タダ働きかよ」
独り言が、虚しく空き部屋に響く。
手元に残る、仕事用の携帯電話。
中には、数多くの番号が登録されている。
コンクリート剥き出しの柱に打ち付けると、あっけ無い程簡単に、携帯は折れた。
突然食い扶持を失っても、気分は何処となく落ち着いていた。
これからどうするかと言う不安と、やっとこの仕事から解放されたという喜びが、平衡したのかも知れない。
幸い、車のローンの支払いは終わったばかり。
偶然目にした自動車学校の看板を見上げながら、自分の行く末を、探した。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(7/8)
二組の布団が、微妙な間隔で並んでいた。
畳敷きの部屋は妙に広くて、少し寂しい感じがする。
窓を開けていると、寒いくらいの潮風が吹きこんで来て、季節感を狂わせた。
「明日、帰るんだろ?」
「うん、秋田から新幹線で」
「あっという間だな」
壁に寄せられた座卓に寄り掛かり、煙草の煙を吹き出す俺に、彼は寂しげな微笑みを見せる。
「もう一泊、してこうか?」
「いや・・・お前の都合もあるだろ?休みも短いんだから」
たまに会うから、こんなに堪らない気分になるのか。
東京へ戻る前の晩は、いつも思う。
こっちに帰って来ようか、と。
そう言う俺に、加賀谷は必ず苦言を呈す。
「仕事なんか、ねぇぞ?タクシーだって、大変だろ。この不景気じゃ」
「そうだろうけど」
でも、そうすれば、いつでもお前の顔が見られる。
そんな言葉を、無理やり飲み込む。
***********************************
「お兄ちゃん、加賀谷さんと知り合いなんだ?」
結婚式の次の日、俺を駅まで送ってくれた妹は、車中でそう聞いて来た。
「ああ、高校で一緒だったんだよ。すげぇ久しぶりに会ったけど」
「その時は、普通だったの?」
幾分怪訝な顔をして聞いてくる妹に、こっちまで訝しげな気分になる。
「何、それ?」
「彼、去年くらいに離婚したんだって」
「・・・そう」
「それがね、浮気が原因らしいんだけど」
「それだけで?」
当然の疑問に、彼女は何処か言いにくそうな口調で事の真相を明かす。
「相手が、男だったって、言うの」
高校3年間の内、加賀谷と寮で同室になったのは3年生の時の1年間。
その間、そんな素振りは一切無かったし、前日会った時にも、変わりは無かった。
「いや、俺は・・・全然」
「もう、家族とも絶縁状態になってるって話だよ」
「そりゃ・・・そうだろうな」
「世間体の為だけに結婚して。自分は男と、遊んでって。最悪」
隣の新妻は、傷つけられた奥さんに自分を重ねているのかも知れない。
ただ、俺にはその経緯が分からない。
ずっと会っていなかったとは言え、旧友のことを一方的に断罪することは出来なかった。
彼の口から事実を聞いたのは、再会から少し経ってのことだった。
「オレは、あの感情が、愛だと思ってたんだ」
彼女と一緒にいたいという気持ち、それは確かだったと言う。
けれど、どうしても身体に手を伸ばすことが出来なかった。
性交渉のない結婚生活に対して不満を感じるのは、当然の成り行きなんだろう。
問い詰められ、自身が同性愛者だと告げた時、彼女はこう言った。
「そんなの、愛じゃない。ただの、エゴだよ」
子供は欲しくない、そう言った彼の言葉を彼女は受け入れてくれたと言うが
彼の心変わりを、何処かで期待していたのかも知れない。
人生の選択の幅が急に狭められたことに、不安を感じたのだろうか。
結局、彼女はしばらくして家を出て行った。
郵送で送られてきた離婚届に判を押し、役所に届け出る頃には、既に他の男の元にいたと言う。
加賀谷が男と浮気したというのは、誰かが流した心無いデマ。
それでも彼は、彼女を悪者にすることなく、一人で全てを被った。
「騙したオレが悪かったんだ。それくらいは、耐えられる」
電話口でそう話す彼の声からは、身を切られるような心情が滲んでいた。
その年の年末、俺は短い帰省をした。
タクシー会社に就職し、ちょうど研修期間中。
生活リズムが上手く形成できず、調子の悪かった身体に、故郷の寒さが堪える。
新幹線のホームには、懐かしい顔が立っていた。
「お疲れ、お帰り」
微笑む表情に疲れた気分が解される。
「ただいま・・・しかし、寒いな」
「今年は雪が少ないからな。それだけ寒いのかも」
「昔、こんなに寒かったっけ?」
「東京の気候に慣れただけだろ?昔に比べれば、大分暖かくなったよ」
そう笑う旧友の車に乗り、彼の家へ向かう。
実家には戻らない。
予め、加賀谷には告げていた。
彼はその理由を聞くことはしなかったけれど、気にかけていることは確かなようだった。
アパートの玄関には、幾つものダンボールが積まれている。
「これ、全部リンゴか?」
つい先日、自宅に送られてきた大量のリンゴを思い出す。
「そ。爺様が送って来るんだよ。米だの、リンゴだの」
彼が実家と絶縁状態にあるのは、事実だった。
その中で唯一、彼の祖父は孫のことを酷く気にかけているようで、事あるごとに連絡をしてくると言う。
「正月だからって、酒と餅も送ってきたから、ちゃんと消費してくれよ?」
自分が抱える過去のことを彼に話したのは、夜も更けて来た頃。
辛苦を誰かと分かち合うことで楽になる、そんな短絡的な思考で及んだ独りよがりな行為。
彼にとっては、迷惑なだけだったはずなのに
何も言わず話を聞いてくれた後、俺の肩を抱き、身体の震えを抑えるように腕を擦ってくれていた。
本当の自分を受け入れてくれた優しさに触れられたからこそ、俺は、今でも前を向いていられる。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
畳敷きの部屋は妙に広くて、少し寂しい感じがする。
窓を開けていると、寒いくらいの潮風が吹きこんで来て、季節感を狂わせた。
「明日、帰るんだろ?」
「うん、秋田から新幹線で」
「あっという間だな」
壁に寄せられた座卓に寄り掛かり、煙草の煙を吹き出す俺に、彼は寂しげな微笑みを見せる。
「もう一泊、してこうか?」
「いや・・・お前の都合もあるだろ?休みも短いんだから」
たまに会うから、こんなに堪らない気分になるのか。
東京へ戻る前の晩は、いつも思う。
こっちに帰って来ようか、と。
そう言う俺に、加賀谷は必ず苦言を呈す。
「仕事なんか、ねぇぞ?タクシーだって、大変だろ。この不景気じゃ」
「そうだろうけど」
でも、そうすれば、いつでもお前の顔が見られる。
そんな言葉を、無理やり飲み込む。
***********************************
「お兄ちゃん、加賀谷さんと知り合いなんだ?」
結婚式の次の日、俺を駅まで送ってくれた妹は、車中でそう聞いて来た。
「ああ、高校で一緒だったんだよ。すげぇ久しぶりに会ったけど」
「その時は、普通だったの?」
幾分怪訝な顔をして聞いてくる妹に、こっちまで訝しげな気分になる。
「何、それ?」
「彼、去年くらいに離婚したんだって」
「・・・そう」
「それがね、浮気が原因らしいんだけど」
「それだけで?」
当然の疑問に、彼女は何処か言いにくそうな口調で事の真相を明かす。
「相手が、男だったって、言うの」
高校3年間の内、加賀谷と寮で同室になったのは3年生の時の1年間。
その間、そんな素振りは一切無かったし、前日会った時にも、変わりは無かった。
「いや、俺は・・・全然」
「もう、家族とも絶縁状態になってるって話だよ」
「そりゃ・・・そうだろうな」
「世間体の為だけに結婚して。自分は男と、遊んでって。最悪」
隣の新妻は、傷つけられた奥さんに自分を重ねているのかも知れない。
ただ、俺にはその経緯が分からない。
ずっと会っていなかったとは言え、旧友のことを一方的に断罪することは出来なかった。
彼の口から事実を聞いたのは、再会から少し経ってのことだった。
「オレは、あの感情が、愛だと思ってたんだ」
彼女と一緒にいたいという気持ち、それは確かだったと言う。
けれど、どうしても身体に手を伸ばすことが出来なかった。
性交渉のない結婚生活に対して不満を感じるのは、当然の成り行きなんだろう。
問い詰められ、自身が同性愛者だと告げた時、彼女はこう言った。
「そんなの、愛じゃない。ただの、エゴだよ」
子供は欲しくない、そう言った彼の言葉を彼女は受け入れてくれたと言うが
彼の心変わりを、何処かで期待していたのかも知れない。
人生の選択の幅が急に狭められたことに、不安を感じたのだろうか。
結局、彼女はしばらくして家を出て行った。
郵送で送られてきた離婚届に判を押し、役所に届け出る頃には、既に他の男の元にいたと言う。
加賀谷が男と浮気したというのは、誰かが流した心無いデマ。
それでも彼は、彼女を悪者にすることなく、一人で全てを被った。
「騙したオレが悪かったんだ。それくらいは、耐えられる」
電話口でそう話す彼の声からは、身を切られるような心情が滲んでいた。
その年の年末、俺は短い帰省をした。
タクシー会社に就職し、ちょうど研修期間中。
生活リズムが上手く形成できず、調子の悪かった身体に、故郷の寒さが堪える。
新幹線のホームには、懐かしい顔が立っていた。
「お疲れ、お帰り」
微笑む表情に疲れた気分が解される。
「ただいま・・・しかし、寒いな」
「今年は雪が少ないからな。それだけ寒いのかも」
「昔、こんなに寒かったっけ?」
「東京の気候に慣れただけだろ?昔に比べれば、大分暖かくなったよ」
そう笑う旧友の車に乗り、彼の家へ向かう。
実家には戻らない。
予め、加賀谷には告げていた。
彼はその理由を聞くことはしなかったけれど、気にかけていることは確かなようだった。
アパートの玄関には、幾つものダンボールが積まれている。
「これ、全部リンゴか?」
つい先日、自宅に送られてきた大量のリンゴを思い出す。
「そ。爺様が送って来るんだよ。米だの、リンゴだの」
彼が実家と絶縁状態にあるのは、事実だった。
その中で唯一、彼の祖父は孫のことを酷く気にかけているようで、事あるごとに連絡をしてくると言う。
「正月だからって、酒と餅も送ってきたから、ちゃんと消費してくれよ?」
自分が抱える過去のことを彼に話したのは、夜も更けて来た頃。
辛苦を誰かと分かち合うことで楽になる、そんな短絡的な思考で及んだ独りよがりな行為。
彼にとっては、迷惑なだけだったはずなのに
何も言わず話を聞いてくれた後、俺の肩を抱き、身体の震えを抑えるように腕を擦ってくれていた。
本当の自分を受け入れてくれた優しさに触れられたからこそ、俺は、今でも前を向いていられる。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
感謝★(8/8)
大きな窓から、仄かな月明かりが入ってくる。
闇の中で、波の音だけが一定のリズムを繰り返す。
静かな夜だった。
こんな静寂、久しぶりかも知れない。
そう、あの夜も、怖いくらいの静けさが身を包んでいた。
俺の身体の上で、腰を振る母の姿。
言い知れない不安を掻き消していく快感。
顔を両手で包み、俺にキスをした母の一言。
「大好きよ、恭一」
暗がりの天井に、その光景が浮かぶ。
何処かでその至上の快楽を求めながら、自分の身体を慰めるおぞましさ。
どうすれば、全てが忘れられるのだろう。
他の人間に心惹かれることは、裏切り、だろうか。
再会から、それほど時間は経っていない。
顔を合わせたのも、ほんの数回。
それでも、彼の声が、言葉が、俺の空虚な心を埋めてくれる。
あの人の存在を覆い隠すほど、もっと、もっと、満たして欲しい。
俺に背を向けて布団に横たわる身体に、目を向ける。
もう、眠ってしまっているかも知れない。
ゆっくりと、その布団に入り込む。
身体に腕を回そうとした瞬間、彼は静かに呟いた。
「どうした?」
止まった手を、彼は振り向くこと無く、自らの胸元に引き寄せる。
「眠れないのか?」
間近に迫った背中に、顔を押し付けた。
微かな鼓動が耳を通って、身体に沁みてくる。
「加賀谷」
「ん?」
「連れてってよ」
「え?・・・何処に?」
「俺の心も、身体も、全部持って・・・一緒に連れてって」
彼の身体の前に回した手に、唇の感触が纏わりつく。
小さな溜め息が、手の甲を滑って行った。
「・・・何処に、行きたい?」
「お前が行くとこなら、何処でも」
「後悔、しないか?」
「しない」
する訳無い。
今以上の地獄がこの世にあるのなら、俺は、全てを諦める。
振り向いた加賀谷の表情は、僅かに逡巡を浮かべていた。
その腕が俺の頭を抱えるように回り、抱き締められる。
「ごめん」
「何が?」
「こんな・・・」
額に唇の感触が滑る。
「謝らなくて、良い」
唇に促され、彼を見上げるように顔を浮かせた。
月明かりが照らす顔が、優しい眼差しで俺を見ている。
「お前の我が侭、受け止めるくらい、訳無いさ」
友達として付き合ってきた男。
心を埋めてくれる、掛け替えの無い存在。
こんな緊張の中で彼の顔を見るのは初めてかも知れない、そう思いながら、唇を重ねた。
何度となくキスをして、身体を触れ合わせる。
直接的な刺激が無くても、心の昂りが止められない。
誰かを好きになるって言うことは、こんな感じなんだろうか。
俺は幸せ者だ。
加賀谷という男に出合い、交友関係を築き、彼と心を通じ合わせることが出来る。
「なあ」
暗がりの中の顔が、俺に目を向ける。
「何?」
その穏やかな表情に、急に不安が頭をもたげた。
甘え過ぎだ。
自制心が、壊れてる。
「・・・いや、何でもない」
「何だよ?気になるだろ」
鼻の頭を擦り付けるように、友の顔が間近に迫る。
「言わないと、何処にも連れてってやんねぇぞ?」
言葉はいらない。
そんなの、嘘だ。
「俺のこと、どう・・・思ってる?」
一瞬驚いた顔を見せた加賀谷は、何かを伺うような表情で問を返す。
「恭一はオレのこと、どう思ってる訳?」
「俺は・・・何でも話せて、すげぇ信頼できる、良い友達で・・・」
「そう言う答で、良いんだ?」
意地悪な口調が、視線を泳がせる。
静かに近づいてくる唇が、耳元で囁きを残した。
「大好きだ。当たり前だろ」
柔らかな色が混ざる海は、今日も穏やかだった。
「加賀谷」
「ん?」
「ありがと、な」
朝日を背に受けた彼の顔が、柔和な笑顔に変わる。
吸い込まれそうになったのは、きっと俺だけじゃなかったんだろう。
「やばい、やばい・・・部屋、戻ろうぜ」
照れを隠すように笑い声を上げた友は、そう言って立ち上がる。
「そうだ、爺様が野菜大量に送ってきたから、ちょっと持って帰ってくれよ」
「だから、食いきれねぇって言ってるじゃん」
「冷凍しときゃ、良いだろ?」
歩く二人の距離は、少し狭まったかも知れない。
記憶のページを一枚一枚閉じて行くことにも、もう迷いはない。
傍を歩く大切な存在の気配を感じながら、俺は実感する。
お前がいてくれて、良かった。
本当に、ありがとう。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<
闇の中で、波の音だけが一定のリズムを繰り返す。
静かな夜だった。
こんな静寂、久しぶりかも知れない。
そう、あの夜も、怖いくらいの静けさが身を包んでいた。
俺の身体の上で、腰を振る母の姿。
言い知れない不安を掻き消していく快感。
顔を両手で包み、俺にキスをした母の一言。
「大好きよ、恭一」
暗がりの天井に、その光景が浮かぶ。
何処かでその至上の快楽を求めながら、自分の身体を慰めるおぞましさ。
どうすれば、全てが忘れられるのだろう。
他の人間に心惹かれることは、裏切り、だろうか。
再会から、それほど時間は経っていない。
顔を合わせたのも、ほんの数回。
それでも、彼の声が、言葉が、俺の空虚な心を埋めてくれる。
あの人の存在を覆い隠すほど、もっと、もっと、満たして欲しい。
俺に背を向けて布団に横たわる身体に、目を向ける。
もう、眠ってしまっているかも知れない。
ゆっくりと、その布団に入り込む。
身体に腕を回そうとした瞬間、彼は静かに呟いた。
「どうした?」
止まった手を、彼は振り向くこと無く、自らの胸元に引き寄せる。
「眠れないのか?」
間近に迫った背中に、顔を押し付けた。
微かな鼓動が耳を通って、身体に沁みてくる。
「加賀谷」
「ん?」
「連れてってよ」
「え?・・・何処に?」
「俺の心も、身体も、全部持って・・・一緒に連れてって」
彼の身体の前に回した手に、唇の感触が纏わりつく。
小さな溜め息が、手の甲を滑って行った。
「・・・何処に、行きたい?」
「お前が行くとこなら、何処でも」
「後悔、しないか?」
「しない」
する訳無い。
今以上の地獄がこの世にあるのなら、俺は、全てを諦める。
振り向いた加賀谷の表情は、僅かに逡巡を浮かべていた。
その腕が俺の頭を抱えるように回り、抱き締められる。
「ごめん」
「何が?」
「こんな・・・」
額に唇の感触が滑る。
「謝らなくて、良い」
唇に促され、彼を見上げるように顔を浮かせた。
月明かりが照らす顔が、優しい眼差しで俺を見ている。
「お前の我が侭、受け止めるくらい、訳無いさ」
友達として付き合ってきた男。
心を埋めてくれる、掛け替えの無い存在。
こんな緊張の中で彼の顔を見るのは初めてかも知れない、そう思いながら、唇を重ねた。
何度となくキスをして、身体を触れ合わせる。
直接的な刺激が無くても、心の昂りが止められない。
誰かを好きになるって言うことは、こんな感じなんだろうか。
俺は幸せ者だ。
加賀谷という男に出合い、交友関係を築き、彼と心を通じ合わせることが出来る。
「なあ」
暗がりの中の顔が、俺に目を向ける。
「何?」
その穏やかな表情に、急に不安が頭をもたげた。
甘え過ぎだ。
自制心が、壊れてる。
「・・・いや、何でもない」
「何だよ?気になるだろ」
鼻の頭を擦り付けるように、友の顔が間近に迫る。
「言わないと、何処にも連れてってやんねぇぞ?」
言葉はいらない。
そんなの、嘘だ。
「俺のこと、どう・・・思ってる?」
一瞬驚いた顔を見せた加賀谷は、何かを伺うような表情で問を返す。
「恭一はオレのこと、どう思ってる訳?」
「俺は・・・何でも話せて、すげぇ信頼できる、良い友達で・・・」
「そう言う答で、良いんだ?」
意地悪な口調が、視線を泳がせる。
静かに近づいてくる唇が、耳元で囁きを残した。
「大好きだ。当たり前だろ」
柔らかな色が混ざる海は、今日も穏やかだった。
「加賀谷」
「ん?」
「ありがと、な」
朝日を背に受けた彼の顔が、柔和な笑顔に変わる。
吸い込まれそうになったのは、きっと俺だけじゃなかったんだろう。
「やばい、やばい・・・部屋、戻ろうぜ」
照れを隠すように笑い声を上げた友は、そう言って立ち上がる。
「そうだ、爺様が野菜大量に送ってきたから、ちょっと持って帰ってくれよ」
「だから、食いきれねぇって言ってるじゃん」
「冷凍しときゃ、良いだろ?」
歩く二人の距離は、少し狭まったかも知れない。
記憶のページを一枚一枚閉じて行くことにも、もう迷いはない。
傍を歩く大切な存在の気配を感じながら、俺は実感する。
お前がいてくれて、良かった。
本当に、ありがとう。
□ 50_感謝★ □
■ 1 ■ ■ 2 ■ ■ 3 ■ ■ 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■
>>> 小説一覧 <<<